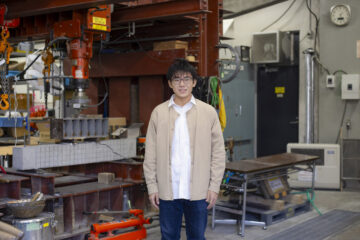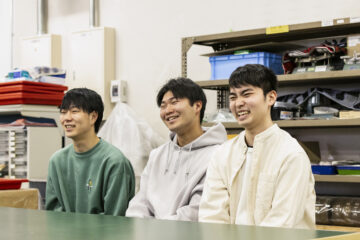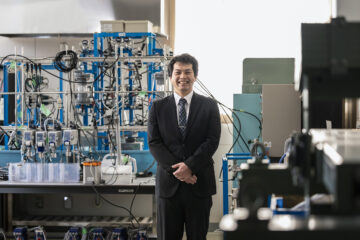【社会環境工学科トピックス: 卒業研究】 酪農大国・北海道が 抱える社会課題に 科学の力で挑む。
水道を主軸に研究する安藤先生の研究室で、畜産系、特に乳牛のふん尿を活用したバイオガス発電プラントから排出される消化液の処理をテーマとした卒業研究に取り組んでいるのが、八谷さんです。水道と畜産系の消化液、一見関わりがなさそうですが、水道の水源となる地下水を守るという観点から、酪農が盛んな北海道では牛のふん尿をどのように処理するかが重大な社会問題です。八谷さんは、安藤先生指導のもと、その課題解決に挑んでいます。
[卒業研究参加](写真左から)
工学部 社会環境工学科4年 八谷 海羽 (北海高校出身)
工学部 社会環境工学科 准教授 安藤 直哉
酪農地域の課題解決に。
――八谷さんが取り組んでいる卒業研究について、どのような内容か教えてください。
【八谷】 牛のふん尿を活用したバイオガス発電プラントから出る消化液の活用について研究しています。北海道の酪農地域では今、酪農家の集約化が進んでいて、小さな牧場がいくつも集まったような大規模な牧場が各地で形成されています。牧場からは毎日大量のふん尿が出るのですが、局地的に発生したふん尿が適切に処理されなければ、地下水や土壌の汚染などさまざまな問題につながります。
すでにバイオガス発電プラントを活用して、ふん尿から発生するメタンガスを発電に使う取り組みも行われていますが、その際に消化液という物質が残ってしまいます。この消化液は90%以上が水分です。運搬するにはコストがかかってしまうため、牧場の近隣に散布されることがほとんど。これを個体と液体に分離させ、固体部分はたい肥として農業に活用、液体部分はそのまま流しても問題のないところまできれいにする、もしくは有用物として循環させることができれば、処理に関する課題が解決できるのではないかといった仮説を立てて実証実験をしています。

【安藤】 八谷くんがいま、熱心に実験を進めている「消化液の固液分離」は、前年の卒業生も取り組んでいたテーマです。彼らの手法を踏まえて、八谷くんは新たにクロスフローろ過の新しい装置を作り、固液分離の自動化に取り組んでいます。
――どうしてこのテーマを選んだのですか?
【八谷】 山鼻キャンパスに来てから、安藤先生の「環境評価論」という講義を履修していました。その授業がきっかけで環境のことに興味を持ち、3年生の時には「環境計測実習」で天然水や水道水の硬度を測ったり、浄水場や下水処理場に行ったりして専門的なことを学びました。研究内容にも興味を持ちましたが、何より安藤先生の人柄にも惹かれて研究室を決めました。安藤先生は、授業以外の場でも気軽に声をかけてくださったので、もっといろいろ教えていただきたいと思いました。
【安藤】 本学科の学生の3分の1近くは、公務員志望です。将来、公務員として地方自治体で働く場合、上下水道のどちらかには必ず関わることになります。ですから学生のうちに学べる環境があるなら、実際の現場を見ておくことが有益な体験になるということで、このような実習を設けているんですよ。
八谷くんが取り組んでいる消化液の研究は、日本の食糧基地である北海道において、どのように食料安全保障を循環させていくかということに視点を置くと、非常に大きな価値のある研究になります。消化液は処理が難しく、液肥として畑に散布する以外の使い方は、それほど研究が進んでいません。研究の成果が出るまでにも時間がかかってしまいますが、続ける価値はあると思っています。
――消化液の研究は、社会的意義が大きいのですね。
【安藤】 このテーマは、水道水源の汚染をどう防ぐかということから派生しています。いま、少し情勢が変化してロシアのウクライナ侵攻を皮切りに、肥料が高騰しているんですね。そこで岸田総理の時代に国交省のもとで、下水から肥料のもとになる窒素やリンを回収しましょうということが進行しています。その点からも、消化液は非常にポテンシャルが高く、農地への還元に期待が持てる魅力的な分野です。国内で肥料の循環と付随して水道水源の保護も達成できるという可能性があります。

大事なのは報・連・相と自ら考え行動すること!実験から社会人の基本を学ぶ。
――実験を続ける中で、難しいのはどんなことですか?
【八谷】 ろ過装置を上手く稼働させるのが難しいですね。消化液は粘度が高いので、ホースがすぐに詰まってしまうんです。一気に流すのではなく、スピードや圧などに気をつけながら流します。それでも詰まったときには、またやり方を変えてということの繰り返しです。
先生からは予め言われていたことですが、研究とは答えがないものに対して仮説を立てて実験し、結果を検証していくものです。自分でしっかり考えていかなければならないところが難しいと感じます。
【安藤】 研究はトライ&エラーです。その過程で大切なのは報(報告)・連(連絡)・相(相談)だと、学生には常に言っています。何かあればすぐに報告してくれれば、一緒に考えることができます。
【八谷】 最初は僕も含めてみんな、壁にぶち当たると一人で抱え込んでいたのですが、最近では相談ができるようになりました。
【安藤】 そうだね。社会に出たら、一人で抱え込むことは通用しなくなるんだよね。研究室もある意味、社会とつながっている場所ですから、何かあれば報告、連絡、相談して研究室のみんなで共有するのが大切なんですね。
――卒業研究での経験が、社会人になってからも役に立つといいですね。
【八谷】 そうですね。僕はゼネコンに就職が内定しており、施工管理者になる予定です。研究を進める中で先生によく言われているのが、考える力を失ってはいけないということです。今後、仕事をする上で報・連・相や考える力は必ず必要になってくると思っています。
【安藤】 八谷くんは民間企業に就職しますが、大学で学んだ人を採用する企業から期待されていることは、将来のリーダーとして仕事をしてもらうことです。自己研鑽を止めてしまっては、成長できません。卒業研究とは、大学生活の最後にそうした実践的な経験をすることができる大事な機会だと思います。

――もうすぐこの研究結果を論文にまとめる時期ですね。
【八谷】 実験の結果を数値化するところまで来ていますが、実用化にはまだ遠い状況です。あとは後輩たちに託したいと思います。そのためにも、後輩たちがやりやすくなるように、まとめていきたいと思います。実用化に向かっての道筋につながればうれしいですね。
【安藤】 最後まで、気を抜かずに頑張っていきましょう!
関連記事
新着記事
-

やりたいこと全部、 自由に打ち込める。 それが2部の学び方。
法学部2部 法律学科3年2部(夜間部) 法律学科 -

<内定先/東京都庁>人生を振り返り 価値観を見直す。 就活で成長を実感。
法学部1部 政治学科4年政治学科 資格・就職 -

<国際交流/韓国>諦めずにやり抜いた経験は この先の人生を 支えてくれる財産です。
人文学部1部 日本文化学科2年国際交流 日本文化学科 -

【法学部トピックス:アカデミック・スキルズ】4年間の学びと その先の人生に通じる 学ぶ技術と姿勢を獲得。
政治学科 法律学科 -

【人文学部トピックス:副専攻課程】夢中になれる 学びをもう一つ 自分のものに。
日本文化学科 英米文化学科 -

<WORLD>新卒から世界へ 海外で働き出して6年目の現在地
日華化学株式会社 グローバル営業推進部卒業生 特集